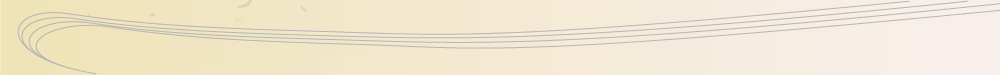今日のブログの主張には個人差があります。一般論、そんなこともあるよねー的な感じで読んでください。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
日本に限ったことではないのかもしれない。
現代、今に限ったことではないかもしれない。
また、人間に限ったことではないかもしれない。
お前は甘い、まだまだ尻の青いガキだ。
それは百も承知の上で・・・
ここ数か月、スポーツ界のパワハラや暴力に関する報道、「訴えるなら今!」的な感じでどんどん出てくる。最初は「そんなことがあるのか!」「様々な困難にある時に、我々に勇気を与えてくれていたあのスポーツで?」「あの人が?」と、裏切られた思いで憤ったり、情けなく思ったり、がっかりもする。
でもね、もううんざり。そして程度の差こそあれ、「スポーツ界に限らないよ。ここだって」とみんなが思っている(に違いない)。
権力と地位を手に入れると、人は傲慢になる。それだけならいいが、常に勝手に敵を作り、排除し、潰しにかかる。それはそうだろう。一度手に入れたものは逃したくはない。優越感に浸れるし、人は寄ってくる。金も入ってくるだろう。だから守りに入る。自分自身もその状況になればそうなるのであろう。俗人であるから。そんな俗人もそのような人をみれば自分を棚に上げて、「そいつは最低の人間だ!自分はそんなさもしい根性は持ち合わせていない」と思うだろう。
しかし、そんな人間は、自分がそんな醜くなっているとは気付かない。周囲の人間も甘いおこぼれに預かろうと媚びを売る。(まあ本気で慕っている人もいるだろうが。)
そして結果「yes-man」が周りを取り囲み、おだてられ、勘違いしていい気になる。
あーやだやだ。
ちょっと外で飲んで帰ってきて、そのまま寝ようと思ったけど、なんかモヤモヤして書き始めたけど、こんな事をブログに書いたところでなんの生産性もないね。
結局何が言いたいかというと、「パワハラは本当に許せない。しかも人格を否定するような発言は。何年経っても心から消えない傷になりますよ。」ということ。
こんな話をご紹介。100年余り一族で経営を続けるとある会社の社長と、その部下となったMの話。
Mは元々、S協会に所属しているとある地方の会社Aの支社に勤めていた。ある時研修のために隣の県にある、A社の本社へ行き、社長のもとで仕事をした。その後Mは更なるスキルアップのために東京の同業種の専門学校へ行く。しかし実地経験も大切、という事で、A社の社長の紹介で、A社と姉妹会社である同じくS協会のB社の社長のもとで働きながら専門学校へ通った。B社の社長は、それはとてもよくしてくれた。また、社長と同等の発言力のある秘書もよくしてくれた。
専門学校で資格を取得すると、B社の社長が、「実はA社の社長からは、M君を頼む、という話で君を受け入れたのだ。将来身の立つようにするから、根回しはこちらでするから、早速家へ来たらどうだ?」と。政治的な駆け引きになれていないMは、その言葉を受けて、A社からB社へ移ったのだ。昨今の体操界の話に置き換えると、引き抜かれたのだ。それまで育ててくれたA社の社長には不義理をしたが、MはB社の社長のもと必死で働いた。多少の理不尽などは気にせず苦にせず、それどころかそれが当たり前だ、と思って働いた。しかし次第に社長と秘書の、Mへの態度は変わっていった。
そして・・・
1.「んまあ、あなたお付きなんだから前に乗りなさい!後ろに乗るってどういうこと!」
移動の際社長とタクシーにのる時、仕事の話や打ち合わせもあるので、社長の希望に従って、まず後部座席に部下Mが先に乗り、その後社長が乗る。これが通常であったそうだ。ある時社長宅から同じ仕事ででかける時、「一緒に行こう。」というので、まず社長宅へ行き、タクシーで向かうことに。部下は社長へ「先に乗りましょうか?」と聞くと、社長は「先に乗って」と。その時タクシーの運転手がみている前で、社長の秘書が発した言葉がこれだ。社長も唖然とした様子だったが、特に何も言わず、部下Mは助手席へ。他人の前で屈辱的な発言を受けた部下は、呆気にとられながらもひきつった顔で約一時間タクシーに乗ったそうだ。
2.「この経歴を見たら、あなたがさも凄い人にみえるじゃない。誰のおかげだと思ってるの?」
これも同じく社長の秘書の発言。部下は対外的に、自分の経歴として毎回同じものを出していたそうだが、なぜかその時は秘書の癇に障ったらしい。
3.「Mをこんな大きなプロジェクトに参加させたら、いい気になるからやめたほうがいい」
これも同じ秘書。これは伝聞。その秘書には気をつけるように(媚びを売れ)アドバイスを受けたそうだ。
4.「あのプロジェクトの話だが、C社の社長から家の後継者であるKあてにきた話なのだが、その日都合が悪いから君を紹介した。」
これは社長の発言。C社の社長は初めからMを指名してきたそうだ。社長はMに恩をきせたかったようだ。ただ、この件はMは何とも思っていないそうだ。なので、一つのエピソードとしてご紹介。
5.「M君あてのD社からの仕事は断っておいた。これは私が最初に頼まれたのだが、都合が悪く断った仕事だ。それを私の部下の君に頼んでくるというのは非常識だ。私より君の方がギャラが安いから頼んできたに違いない。そういう会社には気を付けなさい。」
これも社長の発言。Mが直接言われたことだそうだ。しかし、これもMは別に何とも思っていないらしい。なので、これも一つのエピソード。
Mは結局突然B社を解雇された。10年ほど前の話である。
まだまだ聞いたが、書くのが疲れてきたし、酔いも醒めてきてしまったのでおしまい。
最後にMは言っていた。「今になればつくづく思う。録音しておけばよかった。」と。そして「決して許せはしない」と。
証拠があればパワハラや名誉棄損で訴えられたかもしれないのにね。
ではごきげんよう。